WordPressで始めるSEO対策~初心者が設定すべき6つのポイント~

WordPressでWebサイトやブログを運用していると、「とりあえず記事を書いて公開すればアクセスが集まる」と考えがちです。しかし、実際に優れたコンテンツであっても、検索結果で発見されなければ読まれることはありません。
その解決策となるのが、検索エンジン最適化と呼ばれるSEO(Search Engine Optimization)の対策です。
SEOは専門的で難しそうに思われるかもしれませんが、実はWordPressには初心者でも取り組みやすいSEO設定やツールが多数用意されています。本記事では、SEOの基本的な考え方と、まず初めに設定すべき項目を体系的に解説してまいります。
本記事では、「初めてSEOに取り組む方」「以前から気になっていたが何から始めるべきか分からなかった方」にとって確実な一歩となる内容をご提供します。
1. SEOとは何か?

SEOとは「Search Engine Optimization(検索エンジン最適化)」の略で、GoogleやYahoo!などの検索エンジンで、Webサイトをより上位に表示させるための取り組み全般を指します。
たとえば、あなたが「東京 求人サイト 作り方」と検索したとして、そのときには検索結果の1ページ目にある上から3位に表示されているページが目につきます。そうなった際に、あなたは上に表示された3つのページから選んでクリックしていませんか?
実際にユーザーの多くが上位に表示されるページからサイトを訪れます。
つまり、検索で上位に表示されるということはそれだけ多くの人にサイトを見てもらえるチャンスが増えるということです。
そのため、ブログのアクセスを増やしたい方を含め企業サイトで集客したい方にとっては最も対策しなければならない要素であり、対策を怠るとブログを継続したところで多くの人に閲覧してもらえる機会を逃し続けることになります。
そんな閲覧数を伸ばすために欠かせないSEO対策ですが、大きく分類分けをすると「内部SEO」と「外部SEO」という2つのアプローチに分けられます。これらのアプローチについて特徴を理解することで、これから行う設定や対策が「何のために必要なのか」が明確になります。
1-1. 内部SEOと外部SEOの違い
前章にて、軽く触れましたがSEOには「内部SEO」と「外部SEO」の2つがあります。
この2つは、検索エンジンにサイトの価値を伝える手段として役割もアプローチも異なります。
まず「内部SEO」から説明します。
「内部SEO」を簡単に説明すると、自分のサイトの内部を最適化することを指します。
たとえば、ページの構造を分かりやすく整理したり、見出し(Hタグ)を正しく使ったり、サイトの読み込み速度を改善したりすることがこれに該当します。そのほか、スマートフォンでも見やすいように表示を最適化する「モバイル対応」も内部SEOの一環です。
これらはすべて、検索エンジンがサイトの内容を正しく理解し、評価できるようにするための工夫です。つまり、「このサイトは分かりやすく整っていて、ユーザーにとって有益な情報がある」と検索エンジンに認識させるための土台を整える作業とも言えます。
一方で「外部SEO」は自分のサイトの外側、つまり他のWebサイトやSNSなどからの評価を高める施策のことを指します。代表的なものが「被リンク」と呼ばれるもので他サイトから自分のサイトへのリンクさせることで、他サイトを閲覧している人を自分のサイトへ誘導させる行為のことを指します。こういった誘導を行うことで信頼性の高いサイトからリンクを受けていると、検索エンジンは「多くの人から評価されているサイト」と判断し、検索順位が向上する傾向があります。
ただし、外部SEOは自分の努力だけではコントロールしにくく、地道にコンテンツを充実させたり、自然にリンクされるような発信を行う必要があるので、最初に対策するべきなのは「内部SEO」ということになります。
WordPressを活用するSEO対策のメリット
こうしたSEO対策を行う上で、特に便利なのがCMS(コンテンツ管理システム)でありその中でも「WordPress」はSEO対策において非常に優れています。
その理由としては、WordPressはSEOを意識した構造を持っておりHTMLのマークアップが比較的クリーンで検索エンジンに正確に内容を伝えやすいという特徴があります。
この特徴にプラスしてWordPressに適したプラグインを活用することで、タイトルタグやメタディスクリプションの設定、XMLサイトマップの自動生成、パンくずリストの構造化データ対応など、SEOに必要な施策をノーコードで簡単に実装できます。
加えて、レスポンシブ対応のテーマが豊富に揃っており、モバイルファーストの観点からも評価されやすいサイト構築が可能です。
このように、WordPressはSEO対策に取り組む上で「施策の自由度が高く、かつ効率的に対応できる環境」を提供してくれるため、個人ブロガーから企業サイト運営者まで幅広く支持されています。
次の章からは、初心者でも自ら手を動かして改善できる「内部SEO」に焦点を当て、WordPressでまず押さえておきたい基本的な対策をポイントごとに分けて解説していきます。
2. 【ポイント①】パーマリンク設定の最適化
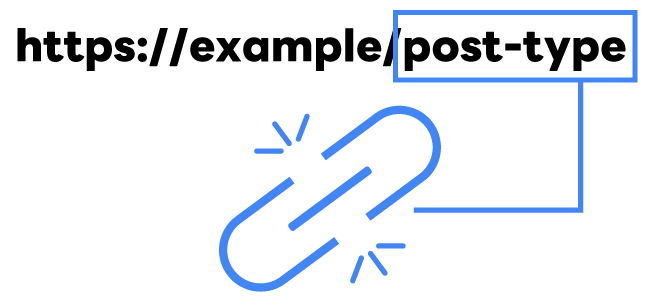
手っ取り早く内部SEOを対策するにはパーリンクの設定を最適化させることが有効です。
パーマリンクとは、各記事や固定ページごとのURL構造のことを指します。
たとえば、ある記事のURLが https://example.com/?p=123 である場合、この「?p=123」の部分がパーマリンクにあたります。
WordPressでは初期状態だとこのような「意味を持たない記号や数字の羅列となっている場合が多く、検索エンジンにとっても、ユーザーにとっても内容が分かりづらくなってしまいます。
このため、パーマリンクはSEOに配慮した形式に変更しておくことが重要です。
そうする理由としては、検索エンジンはURLに含まれる単語も手がかりにして、そのページの内容を判断しているからです。
これは、人の目から見たときも同様でタイトルに関連した語句がURLに含まれていれば、そのリンク先にどのような内容があるかがひと目で分かりやすくなります。
そのため、パーマリンクは「投稿名」などの、ページの内容が視覚的にも内容が直感的に理解できる語句が含まれる形式に変更するのが基本的なSEO対策です。
WordPressでは、管理画面の「設定」>「パーマリンク」から形式を変更することができるので初心者の方にも扱いやすくなっています。
最も一般的な設定は「投稿名」形式で、たとえば「会社概要」という固定ページを作成した場合、https://example.com/company/ のようなURLが生成されるようになります。これにより、検索エンジンにとって内容が明確に伝わりやすくなり、ユーザー目線でもこれは会社概要のページだと視覚的にわかりやすくなることで安心してクリックできるようになるので基本的には「投稿名」形式がおすすめとなります。
少し慣れている中級者の方には、より細かく構造を管理するためにカテゴリや日付をURLに含めたいと考える方もいるかもしれません。たとえば、「/blog/webdesign/post-name/」のように「ページ名/カテゴリー名/投稿名」のような形式があるとします。このような形式は、サイト全体の構造を明示するという意味では有効である反面、カテゴリを変更するとURLも変わってしまうリスクがあるので更新頻度や運用体制をふまえて慎重に判断する必要があります。
パーマリンクの注意点として、サイト公開後にパーマリンクの形式を変更すると既に検索エンジンに登録されたURLや外部サイトからのリンクが無効になってしまう可能性があります。したがって、パーマリンク設定はできるだけサイト立ち上げ初期の段階で整えておくことが重要です。万が一運用中に変更が必要となる場合は、リダイレクトの設定などを含めて慎重に対応する必要があります。
このように、パーマリンクは一見些細な設定に見えるかもしれませんが、検索エンジンからの評価やユーザー体験に密接に関わる、非常に重要な要素のひとつです。SEO対策の第一歩として、最初に見直しておきたいポイントです。
3. 【ポイント②】タイトルとメタディスクリプションの最適化

SEOにおいて、ページタイトルとメタディスクリプションの最適化は極めて重要な役割を担います。
これらは、検索結果画面に表示される情報の中でも特に目に留まりやすい部分であり、ユーザーがクリックするかどうかを左右する要素でもあります。
まず、ページタイトルについてですがこれは単なるページの名前ではなくそのページの内容を端的かつ魅力的に伝える役割を持っています。検索エンジンはタイトルに含まれるキーワードを重視しているため、タイトルを内容に合わせた適切なものへ設定することでSEO効果を高めることができます。
そのため、ここではタイトルを作成する際のポイントについてご紹介していきます。
3-1. ページタイトル
まず、真っ先に気を付けるポイントとしてはページタイトルに狙っているキーワードを自然に含めることです。
たとえば「WordPressのパーマリンク設定」について検索するユーザーを想定するならば、「WordPress パーマリンク 設定方法」といった具体的な語句をタイトル内に自然に織り交ぜることで、検索結果に表示されやすくなります。
次に、タイトルの文字数にも注意が必要です。一般的には30〜35文字程度に収めると、検索結果で途切れずに表示されやすくなります。必要以上に長いタイトルは読みづらくなり、クリック率が下がる傾向にあるため、簡潔かつ具体的な表現を心がけましょう。
3-2. メタディスクリプション
メタディスクリプションとは、ページの要約文にあたるものです。検索エンジンが自動で生成することもありますが、自分で適切に設定することで、より正確にページ内容を伝えることができます。
メタディスクリプションは、直接的に検索順位に影響を与えるわけではありませんが、検索結果画面でユーザーに選ばれるための「説明文」として非常に重要です。
ここでも、記事の要点を簡潔にまとめることを意識し、70〜120文字程度に収めるのが理想です。ユーザーが「この記事は自分の知りたいことが書かれていそうだ」と感じられるような文章を目指しましょう。
また、自然な形でキーワードを含めることによって、ユーザーと検索エンジンの両方に対してページ内容を明確に伝えることができます。
WordPressを使っている場合、多くのテーマやプラグイン(例:All in One SEO Pack、Yoast SEOなど)でタイトルとメタディスクリプションを個別に設定することが可能です。これらを活用し、記事ごとに丁寧に設定を行っていくことで、SEO効果だけでなく、サイト全体の信頼感向上にもつながります。
タイトルとメタディスクリプションの最適化は、地味に思えるかもしれませんが、検索結果から自サイトへの入口を広げるための極めて重要な施策です。記事を公開するたびに、必ず意識的に見直す習慣をつけましょう。
4. 【ポイント③】見出しタグ(H1〜H3)の適切な使いわけ
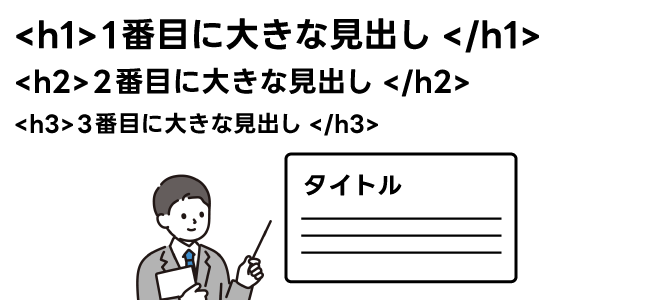
Webページにおいて「見出しタグ(Headingタグ)」は、情報の構造を明確にするための重要な役割を担っています。検索エンジンに対してページ内容の階層や重要度を伝えるだけでなく、読者にとっても文章を素早く把握しやすくする効果があります。
WordPressの記事作成画面で使用される「H1〜H3」の見出しタグは、それぞれに意味と役割があります。
H1はページ内で最も重要な見出しであり、通常は記事のタイトル部分に1度だけ使われます。WordPressではテーマ側で自動的にH1が記事タイトルに適用されていることが多いため、本文中であらためてH1タグを使う必要はありません。
その次に重要なのがH2タグです。H2はページ内の大きなトピックや章の区切りとして使用されます。
たとえばこの記事のように、「【ポイント③】見出しタグ(H1〜H3)の適切な使いわけ」といった大見出しがH2に該当します。その下にある細かい説明や補足情報には、H3タグを使うことで構造がより明確になります。そのため、H3はH2の内容をさらに分割する小見出しと考えると分かりやすいでしょう。
こういった見出しタグは、ページ全体を論理的な構造で整理するために用いるものであるので、検索エンジンはこの構造をもとに、ページがどのような内容で構成されているかを理解し、適切にインデックスします。適切に使うことで、SEOの評価を上がりユーザーにとっても読みやすくなることで離脱率の低下にもつながります。
注意すべき点としては、順序を飛ばさないことです。H2の下にいきなりH4を使ったり、見出しの階層を乱すと、検索エンジンはページ構造を正しく認識しにくくなります。また、見出しには単なる装飾や強調の目的で使うのではなく、意味のある区切りとして活用することが基本です。
このように、見出しタグの使い方ひとつを取っても、サイト全体の情報設計や検索エンジンからの評価に大きな影響を与えます。WordPressでは視覚的に簡単に設定できるため、記事構成を意識しながら積極的に活用していくことが、SEOにおける基本姿勢と言えるでしょう。
5. 【ポイント④】 画像の最適化(alt属性・ファイル名・圧縮など)
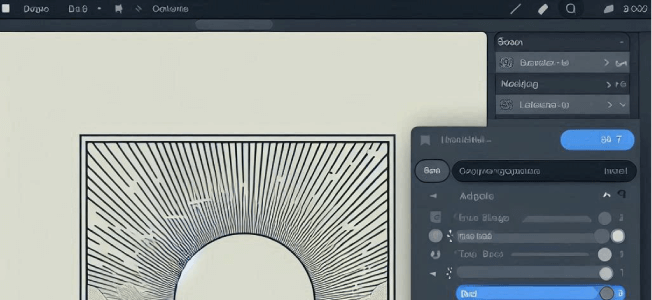
画像は、Webサイトにおける視覚的訴求力を高め、コンテンツの理解を補助するうえで不可欠な要素です。しかし、適切に最適化されていない画像は、ページ表示速度の低下や検索エンジンによる評価の減少を招く恐れがあるため、SEO対策の一環としても軽視できないポイントとなります。
本章では、画像最適化における具体的な取り組み事項として、「alt属性の設定」「ファイル名の適正化」「画像圧縮」の3点に焦点を当てて解説いたします。
5-1. alt属性(代替テキスト)の適切な設定
alt属性とは、画像が表示されない環境や、視覚に障がいのあるユーザーがスクリーンリーダーを使用する場合に、画像の内容を説明する役割を果たすテキスト情報です。検索エンジンは画像を外見にて中身を判断できないため、alt属性に記述されたテキストをもとに画像の意味を判断するので、画像を入れる際はalt属性の記述を忘れるとおのずとSEOの評価が低下してしまう恐れがあります。
画像の内容を簡潔かつ具体的に記述したalt属性の設定はSEO強化に加えてアクセシビリティの向上にもつながるので、特に情報性の高い画像(例:図表・グラフ・操作画面キャプチャ)においては、内容を正確に伝える記述が重要になります。
5-2. ファイル名の適正化
画像のファイル名も、SEOにおいて無視できない要素の一つです。たとえば、「IMG_001.jpg」のような自動生成された名前では、画像の内容を検索エンジンに伝えることができません。
この点、「wordpress-theme-sample.jpg」のように、内容を明示し、適切なキーワードを含んだファイル名を設定することで、画像検索における可視性が高まり、コンテンツとの関連性も明確になります。ファイル名は半角英数字で記述し、単語の区切りにはハイフン(-)を使用するのが一般的な慣例です。
5-3. 画像サイズと圧縮による軽量化
ページ表示速度はユーザー体験に直結する要素であり、検索順位にも影響を与える重要な指標です。特に複数の画像を含むページでは、画像ファイルの容量が全体の読み込み速度に大きく影響します。
したがって、以下の対策を講じることが推奨されます。
- 画像サイズを適切にリサイズ(表示領域に合わせた解像度に調整)
- 圧縮ツール(例:TinyPNG、Squoosh)によるファイル容量の削減
- WordPress利用時には「EWWW Image Optimizer」などのプラグインによる自動最適化の導入
これらを実施することで、表示速度の改善はもとより、ユーザーの離脱防止や直帰率の低下にもつながります。
画像の最適化は見落とされがちですが、検索エンジンとユーザーの双方に対して、コンテンツの質と信頼性を高めるうえで非常に効果的な手段です。特にブログ記事が多くなるほど、蓄積される画像の数も増えるため、初期段階から適切に整えておくことが重要です。
6. 【ポイント⑤】 モバイル対応と表示速度の改善
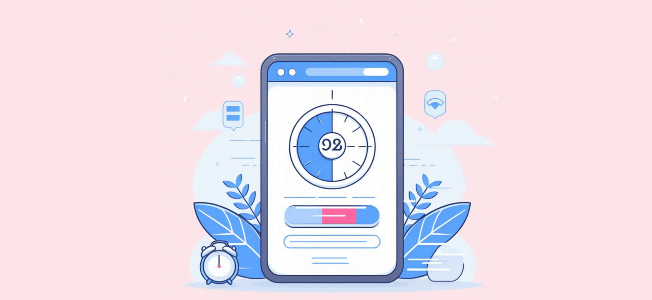
現代のWeb環境において、スマートフォンによる閲覧が主流となっている現在、モバイル対応の有無はSEO評価における重要な指標の一つとなっています。Googleをはじめとする検索エンジンは、モバイルフレンドリーな設計であるかを評価基準に組み込んでおり、ユーザー体験の最適化を重視する姿勢を明確に打ち出しています。
6-1. モバイル対応(レスポンシブデザイン)の確認と調整
WordPressでは、多くのテーマがレスポンシブデザインに対応しているものの、実機での確認は欠かせません。以下の点について定期的な検証を行うことが推奨されます。
- 文字サイズの可読性
小さすぎるフォントは離脱の原因となるため、スマートフォンでの視認性を確保する。 - タップ領域の確保
ボタンやリンクの間隔が狭すぎると、誤操作の原因となります。十分なタップ領域を設けることが重要です。 - レイアウト崩れの有無
異なる端末サイズで表示が乱れていないか、定期的に確認を行うこと。
Googleの「モバイルフレンドリーテスト」などのツールを活用することで、技術的な対応状況も把握できます。
6-2. 表示速度の最適化によるユーザー体験の向上
ページの表示速度は、ユーザーの離脱率および検索順位に直結する重要なファクターです。特にモバイル回線では回線速度に制限がある場合も多いため、サイトの軽量化は最優先事項と言えます。
具体的な対策として、以下のような改善策が挙げられます。
- 画像の軽量化
不要に高解像度な画像の使用を避け、前述の通り圧縮やリサイズを実施。 - プラグインの精査
使用していない、または重複しているプラグインを削除することで、サイトの処理負荷を軽減。 - キャッシュの活用
WP Super CacheやLiteSpeed Cacheなどのキャッシュ系プラグインにより、サーバー負荷と読み込み時間を削減。
6-3. 中・上級者向け:CDNおよびサーバー性能の見直し
アクセス数の増加やコンテンツの拡充に伴い、さらに高度な施策として以下を検討すると更なる表示速度の向上につながります。
- CDN(Content Delivery Network)の導入
グローバルに分散されたサーバーから静的ファイルを配信することで、地域による表示速度の差を解消。 - 高性能サーバーの選定
共用サーバーからVPS、クラウド型への移行も視野に入れることで、応答速度や処理能力の向上が図れます。
7. 【ポイント⑥】内部リンクの構造化とナビゲーションの工夫
SEOを強化するうえで、サイト内部のリンク構造を戦略的に設計することは極めて重要です。
検索エンジンは、ページ間のリンク関係を通じて情報の体系性やコンテンツの重要度を評価するため、内部リンクを適切に活用することで、クローラビリティ(検索エンジンによる巡回性)とユーザー体験の双方を高めることが可能となります。
7-1. 内部リンクの設計と活用
内部リンクとは、同一ドメイン内の他のページへリンクを張ることを指し、主に以下のような効果があります。
- 検索エンジンにページ同士の関係性を明確に伝える
- 特定ページへの評価(リンクジュース)を適切に分配する
- ユーザーの回遊性向上と滞在時間の延長を促進する
たとえば、ある記事内で関連する過去記事やカテゴリーページへのリンクを文脈に沿って自然に挿入することで、読者はより深い情報にアクセスしやすくなります。このような内部リンクは、単なるナビゲーションではなく、「コンテンツ間の論理的つながりを補強する情報設計」の一環と捉えることが重要です。
WordPressを利用している場合、プラグイン(例:Yoast SEOやInternal Link Juicerなど)を活用することで、効率的な内部リンク管理が可能です。また、記事冒頭の目次や文末の「関連記事」も、自然なリンク導線として非常に効果的です。
7-2. ナビゲーション設計の最適化
サイト全体のナビゲーションも、ユーザーと検索エンジンの双方にとって不可欠な導線です。以下の要素を整理し、情報構造の明確化を図りましょう。
- ヘッダーメニュー:主要カテゴリーや固定ページへのリンクを集約し、サイトの方向性を直感的に示す。
- パンくずリスト:現在のページの位置を階層的に示し、上位カテゴリへのスムーズな移動を促す(Googleもパンくずリストを評価対象としています)。
- サイドバーウィジェット:人気記事や最近の投稿、カテゴリーリンクなどを表示することで、回遊性を高める。
これらの要素は、訪問者にとっての「迷わないサイト」を構築するだけでなく、検索エンジンのクロール効率を高め、インデックス精度の向上にも貢献します。
8. まとめ
WordPressを活用したSEO対策は一見専門的に感じられるかもしれませんが、実際には日々の運用における基本的な設定と習慣の積み重ねこそが、大きな成果へとつながる重要な要素です。
本記事でご紹介した各ポイントは、どれも初心者の方でも実践可能でありながら検索エンジンからの評価を中長期的に高めるための有効な施策です。SEOとは一度対応して終わりではなく、サイトの成長や環境の変化に応じて定期的な見直しと改善を行うべき継続的な取り組みです。
まずは基本を正しく理解し小さな一歩から着実に積み上げていくこと。
これこそが検索エンジンからの信頼を獲得しユーザーにとって有益なWebサイトへと導く最も確実なアプローチであると言えるでしょう。
-
前の記事
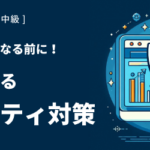
“狙われる前に備える” WordPressセキュリティ強化ガイド 2025.04.16
-
次の記事

GoToRecruitアップデート!大きく変わった3つの要素を解説します 2025.09.30


